
理念・指導コンセプト
philosophy
自発的選手の育成
自発的選手の育成
子どもが変わる瞬間を作る

「サッカーって楽しい!」
仲間とボールを蹴り、協力し成功した喜びや爽快感に満ちた気持ちは忘れられない思い出になるはずです。純粋にサッカーを楽しんでもらいながら子供たちの心にスイッチを入れます。
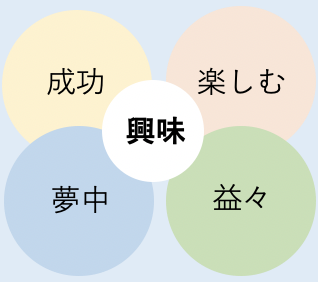
「もっと上手くなりたい」
誰かに言われるからではなく、自分から「学びたい!」と思える姿勢を育むことが根本的な目標です。
子どもたちの「姿勢」と「習慣」を変え、真のサッカースキルを身につけさせます。
concept
スキルを習得するための「制約主導」トレーニング
スキルを習得するための「制約主導」トレーニング
「感覚」「教えられる」だけでは、なぜ限界があるのか?

「自ら考え言動する」
ヨーロッパや南米のサッカー先進国の子供たちは、根本的にサッカーの本質の理解定着が深く浸透しています。
幼い頃から試合に勝つためには、「どのように協力して相手を上回るか」を選手たち自らが話し合う習慣が身に付いているからです。
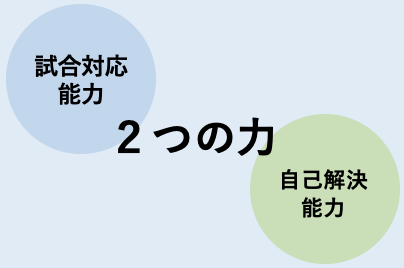
「瞬時に判断し最適なプレーを選択」
サッカーの構造を理解するための導きを行い、「自己解決能力」と「試合対応能力」を身につけるために、対話する習慣が必要になります。
2つのキーファクター
認知
サッカーにおいて最も重要な【状況を把握する】動作。
・どこにスペースはあるのか
・どこに相手がいるのか
・どこでボールを受けるのか
・いつ動き出すのか
・いつボールを回収しに行くのか
etc…
主に上記の内容を目で観て情報を脳に送り、瞬時に状況判断を繰り返す。
・どこにスペースはあるのか
・どこに相手がいるのか
・どこでボールを受けるのか
・いつ動き出すのか
・いつボールを回収しに行くのか
etc…
主に上記の内容を目で観て情報を脳に送り、瞬時に状況判断を繰り返す。
間接視野
認知の質を高めるためには、【間接視野】の習得が必要不可欠。
目まぐるしく状況が変わるサッカーでは、一つのものを直視するのではなく、複数の項目を同一視野に入れ、判断を繰り返す動作が必須になってきます。
目まぐるしく状況が変わるサッカーでは、一つのものを直視するのではなく、複数の項目を同一視野に入れ、判断を繰り返す動作が必須になってきます。
6つのアクション
観る
サッカーにおける「原理原則」のファーストステップで最も重要と言ってもよい【観る】という動作は、”スペースはどこにあるのか”、”どこに相手がいるのか”、”どこでボールを受けるのか”、”いつ動き出すのか”、”いつボールを回収しに行くのか”、目で観た情報を脳に送り、瞬時に「判断」するトレーニングを徹底的に行い、習慣化します。
止める
スペース、相手、味方の位置を認知していれば適切な身体の向きを整えることができます。そうすることでボールを止める位置や角度を考え、状況に応じて意図する場所に正確なトラップができます。つまり試合を想定した相手がいる状況のトレーニングで、いかに正確にボールを【止める】ことができるかが重要です。日々のトレーニングで精度を磨きます。
蹴る
ドリブル、パス、トラップ、シュート、足の部位を使い、いくつかの種類のキックと強弱で状況に応じて選択し、使い分けをしなければいけません。様々なトレーニングの中でキックのアイデアを増やせるようにアプローチします。
運ぶ
「蹴る」と同様、サッカーにおいて重要な技術で、ドリブルには、”運ぶ”と“仕掛ける”の2種類があります。
ビルドアップでは相手がいないスペースでボールを保持している場合、運ぶドリブルで相手を引きつけてパスを選択し数的優位な状況を作り出したり、相手がパスを予測している場合には、状況を認知して自ら運ぶドリブルで局面を打開したり、効果的なドリブルのスキルを習得します。
ビルドアップでは相手がいないスペースでボールを保持している場合、運ぶドリブルで相手を引きつけてパスを選択し数的優位な状況を作り出したり、相手がパスを予測している場合には、状況を認知して自ら運ぶドリブルで局面を打開したり、効果的なドリブルのスキルを習得します。
取り返す
ボールを失った際には、ボールを取り返さないと攻撃ができません。そのためには相手のミスを誘うためにプレッシャーをかけることが不可欠です。まずは個人が、どのタイミングで、どんな方法でボールを取り返すのかを理解することが重要です。それを理解した上でグループとしてのボールの取り返し方を試合と同条件のトレーニングを繰り返し行うことで、守備においても精度を高めます。
メンタル
個人が成長する過程で、とても重要な要素です。サッカーにおいて原理原則を理解し習得することは勝敗を左右する上で大切ですが、最終的に選手一人ひとりの精神的強さが勝負を決定づける場合もあります。
サッカーに対する想いや志を強く持ち、日々のトレーニングを全力で取組むことで強さを積み重ねることができ、大きな飛躍の鍵となります。
サッカーに対する想いや志を強く持ち、日々のトレーニングを全力で取組むことで強さを積み重ねることができ、大きな飛躍の鍵となります。
